福井バイパス沿いにあり車でのアクセス良好な福井県ナースセンターには、日々多くの看護職が相談や研修に訪れます。求職者からも求人施設からも頼りにされるナースセンターとして、日々どのような活動を行っているのでしょうか。福井県ナースセンターの水嶋奈美代さん、中江円香さん、山田文子さんにお話を伺いました。
再就職を目指す看護職にどのような支援を行っているのですか。
水嶋 まずは、嶺北会場(福井県看護協会)と嶺南会場(二州健康福祉センター)の2カ所で年に3回ずつ開催している再就業講習会ですね。2016年度には32人の再就業希望者が参加し、2017年2月末時点で15人が再就職しています。残りの方も精力的に施設を見学して回っている段階です。
この再就業講習会は、現場に出る前に再確認しておきたい最低限の知識を全4回(嶺南会場では全2回)かけて網羅するもので、特定の分野だけ学びたいというニーズも受け入れますが、ほとんどの人が全課程を修了しています。参加者の中心は、小さなお子さんがいて離職中の30代から40代の方です。お子さんを保育園や幼稚園に預けて参加しやすいよう、講習会は週1回のペースで10時スタートというかたちを取りました。参加者には再就業にとても前向きな方が多く、受講後のアンケートでも「最新の知識が学べてよかった」「絶対に頑張って就職したい」という声が多く聞かれました。今後は、講習会の回数を増やしたり、内容をさらに充実させたりしていきたいです。

中江 お子さんが小さい間は、土日祝日はお休み、平日9時から15時くらいの間で働きたいという希望が多いのですが、このような条件の求人は普通、簡単には見つかりません。連携している各地のハローワークからの情報とナースセンターが持つ情報を合わせて、ベストの就職先を探します。このとき、再就業希望者とじっくりお話しして希望にかなう職場かどうかよく確かめることが、就職率を上昇させ、退職率を低下させる要になります。
ナースセンターに相談に見えた方には、まず求職登録票に記入をお願いして、希望する条件や就職したい時期についてなどを当センターのスタッフ間で共有するようにしています。そして、例えば「○月から働きたいという希望だったのに、時期が迫っても姿が見えない」というような人がいれば、電話連絡などをして積極的に支援していくわけです。
また、再就業後のフォローも欠かせません。「何かあったら退職に至る前に相談してね」とお伝えしておき、人間関係や仕事について悩みが生まれたときには、いつでも相談してもらえるように配慮しています。

水嶋 2010~2014年度に県の委託でナースサポーター設置事業が行われ、ナースセンターが県内の病院・診療所や高齢者施設など年間100件以上の施設を訪問し、生の声を聞き取りながら情報を集めてきました。もちろん、この事業が終了した後も各施設を年に30~40件程度は回り、情報を更新し続けています。当センターのスタッフが各施設の長や担当者となじみの関係になることで、それぞれの職場の状況や、どのような看護職を求めているかといった点を細かく把握できているわけです。
それと同時に、看護職の定着に頭を悩ませている施設が多いため、具体的事例を盛り込んだ『看護職確保・就業・定着のためのワンポイントアドバイス』を作成し、ナースセンターからサポートする事業を行っています。
南北に長い県を広くカバーするために、嶺南地区にサテライトを設けたそうですね。
水嶋 2016年4月に設置された嶺南サテライトでは、毎週火曜日に相談事業を実施しています。県庁所在地・福井市のある嶺北地域に比べて、これまで嶺南地域へは就業支援の手が届きづらかったのですが、徐々に相談のニーズも増えて活性化してきた印象です。嶺南地区では退職した看護職が地元の口コミに頼って再就職先を見つけるケースが多く、ブランクがある方への支援は手薄な状態でした。嶺南サテライトで相談したり再就業講習会を受講したりすることで、「また働いてみたい」という思いの芽生える人が増えればと願っています。
また、2015年度からは県内6カ所にあるハローワークすべてとの連携体制を整えており、情報交換しながら求職者への支援を行っています。各ハローワークへ出張しての相談会も開催しており、福井市まで出て来なくても当センターの相談員と話していただくことが可能です。知名度抜群のハローワークを通してナースセンターの存在を知っていただけるという広報的な効果も期待しています。
「訪問看護支援室」があるそうですが、具体的にどのような活動をしていますか?
山田 訪問看護支援室では、訪問看護に興味がある方への相談対応や再就業支援、研修のほか、県内の訪問看護ステーションの実態調査なども行っています。県内の訪問看護ステーションの事業所数は、2008年には約50件だったものが現在では80件近くまで増えており、訪問看護は多様な経歴を持つ看護職が活躍できる領域としてきわめて有望だと考えています。

従来は「訪問看護師になるのは経験を積んだベテラン看護職」という固定観念があったのですが、現在では若いうちに訪問看護の世界に飛び込む人も少なくありません。それを受け入れる訪問看護ステーションの側にも、質の高い教育システムを構築し、看護職の職場定着を図ることが求められています。特に大切なのは、新人職員の居宅訪問に同行して指導する期間をきちんと設けることです。
こうした背景から、訪問看護支援室では「チャレンジ就業」という制度を用意しています。希望する訪問看護ステーションで所定の給与を受けながら、2カ月にわたり試験的に就業できるというものです。県から補助が出るので施設側も金銭的な負担が少なく、2カ月間じっくりと新人教育に取り組むことができます。2016年度は16人がチャレンジ就業して、そのうち14人が実際に就業し、現在も訪問看護師として活躍しています。
在宅医療に関連しては「退院支援研修プログラム」も人気ですね。入院日数が短縮傾向にある今、病院勤務の看護職も「在宅医療へのスムーズな移行を実現する」という視点で患者さんを支える必要があります。このプログラムでは4日間かけて退院支援について学びますが、そのうち1日は地域包括ケアセンターでの実習としています。2016年度には、定員30人のところ45人もの参加者が集まりました。入院医療から在宅医療へのつなぎを重視し、患者さんを支える医療資源などについて積極的に学びたいと考える看護職が増えていることは、とても好ましい流れだと考えています。
最後に、福井県で再就業を目指す看護職の皆さんへメッセージをお願いします。
水嶋 県民性のためなのか、福井県にはおとなしく控えめな性格の人が多いような気がします。だからこそ、相談を受ける際には、落ち着いた雰囲気の中でゆっくりと傾聴することが欠かせません。当センターには、パーテションで区切られた相談コーナーのほか、プライバシーが守れる完全個室の相談室も用意されています。こうした環境で信頼関係を築く中で、1時間以上にわたって悩み相談を持ちかけてくれる人、毎日のように電話をかけてくれる人もいます。
再就業を目指す皆さんにお伝えしたいのは、必ずしも焦る必要はないということ。1年以上かけて就職活動を続け、希望通りの職場を見つけるケースも少なくありません。きめ細かな支援を継続できるのが当ナースセンターの強みですから、まずは気軽に会いにきてもらい、一緒に次の道を探していければと思っています。
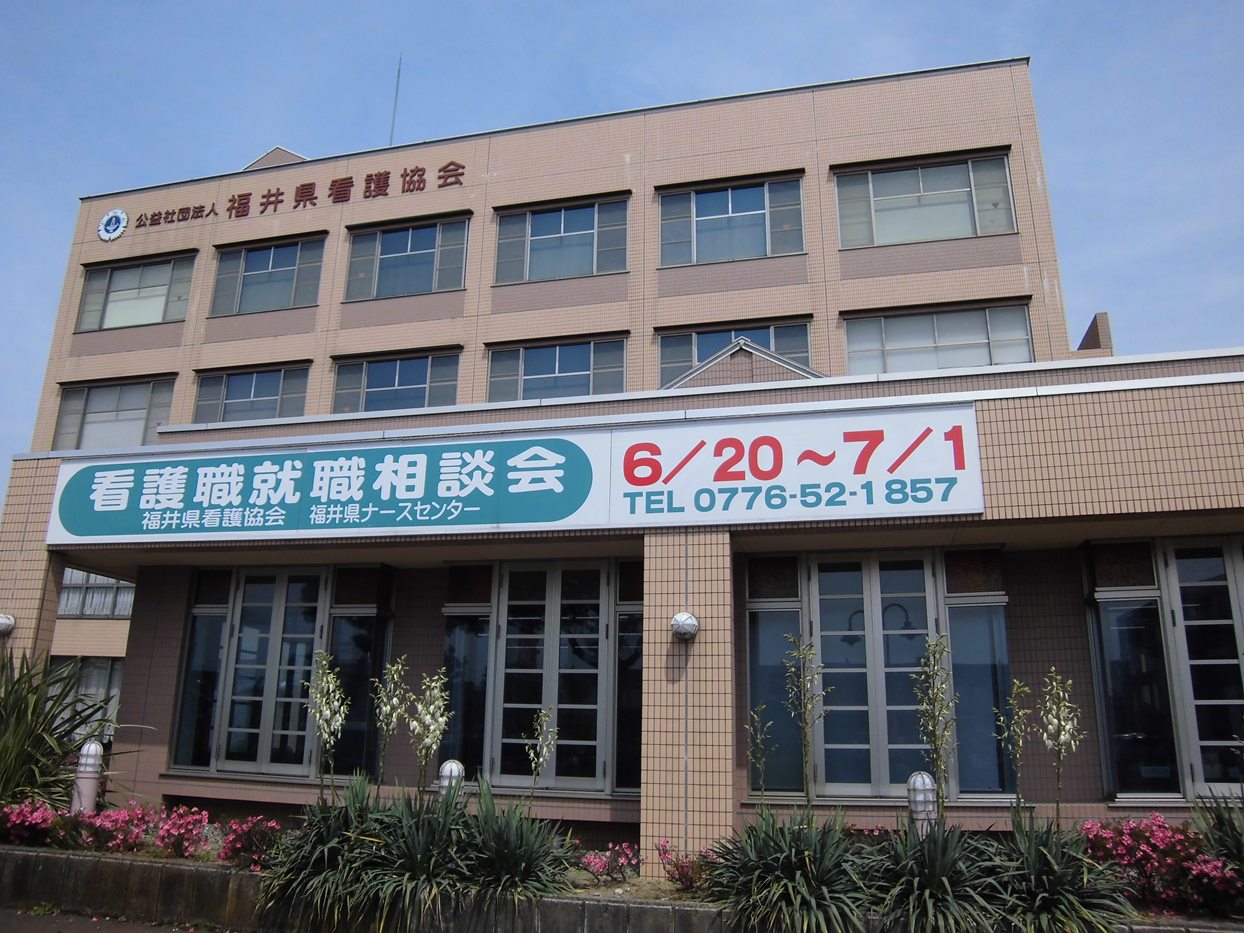
福井県ナースセンター
〒918-8206 福井県福井市北四ツ居町601
TEL 0776-52-1857
http://www.kango-fukui.com/publics/index/9/
●センターの主な事業内容
・無料職業紹介
・嶺南サテライト事業
・届出制度周知と関係機関への届出協力依頼
・再就業講習会
・ハローワークとの連携・出張相談会
・就職相談会
・「看護の心」普及事業(「看護職への道」講演会、一日看護体験)
・看護学生インターンシップ事業
・在宅看護人材キャリアアップ事業(訪問看護師養成講習会、退院支援研修)
●センターで今一番注力している事業
・未就業者の再就業に向けての相談・支援
・再就業講習会
・ハローワーク出張相談会
・就職相談会
・届出制度の周知と届出者への支援
・嶺南サテライト事業
●今後行いたい取り組み
・再就業講習会:求職者がいつでも受講できるよう、講習会の回数を増やす。嶺南地区からも参加しやすいよう、嶺南サテライトでも実施する。看護技術に対しての不安が軽減できるよう、採血や吸引の実技演習も実施する。
・ナースセンター周知のための広報活動:より多くの看護職の方にナースセンターを知っていただくため、看護協会とナースセンターの広報誌の発行回数を増やすとともにナースセンターをPRする記事を掲載する。特に2016年に開設した嶺南サテライトのよりいっそうの周知を図る。
●離職者へのメッセージ
私たちナースセンターは、育児や介護など様々な事情を抱える中で自分に合った仕事を探す方の思いを聞いて細やかに対応し、希望に沿った就職先を探すお手伝いをさせていただいています。
●その他のアピールポイント
福井県ナースセンターでは「働きたい!看護職のあなた」を応援しています。ブランクがあり再就職に踏み切れない方、子育てをしながら短時間でも働きたい方、離職しようか迷っている方など、就業中・未就業を問わずに手厚い支援を行っています。お気軽にご相談ください。








